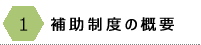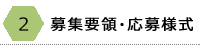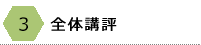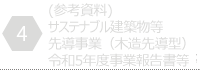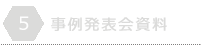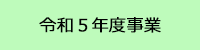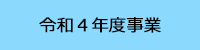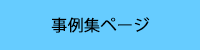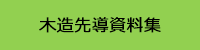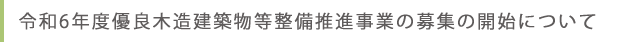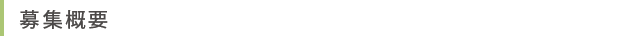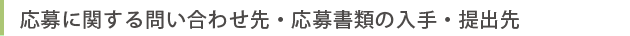令和6年度住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業のうち「優良木造建築物等整備推進事業」について、当事務局において令和6年度第1回目の提案の募集を開始することとしましたので、お知らせします。
提案応募及び補助金を受給される皆様へ
令和6年度住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業のうち「優良木造建築物等整備推進事業」について、当事務局において令和6年度第1回目の提案の募集を開始することとしましたので、お知らせします。
提案応募及び補助金を受給される皆様へ
本募集要領で募集する事業に対する補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本募集要領による募集に応募される方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下、「適正化法」という。)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただく必要があります。
本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消等を行う場合があります。
- 1 応募者及び補助金交付申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。
- 2 交付決定された優良木造建築物等整備推進事業に関し、国土交通省、評価事務局※1又は実施支援室※2から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消等を行うことがあります。
※1:優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局
※2:優良木造建築物等整備推進事業 実施支援室 - 3 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
- 4 補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。
- 5 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
- 6 採択又は交付決定された事業内容からの変更は、原則、認められません。
- 7 補助事業にかかわる資料(応募並びに交付申請に関わる書類、その他経理に関わる帳簿及び全ての証拠書類)等は、事業完了の属する年度の終了後、5年間保存していただく必要があります。
- 8 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について、大臣の承認を受けなければなりません。
- 9 事業完了後も、本募集要領に規定する適正な財産管理、木造化に関する積極的な普及啓発などが必要です。
1. 公募するプロジェクト
令和6年度から、本事業に「普及枠」と「先導枠」を創設しました。次の①②のいずれかの要件に適合するプロジェクトを募集します。なお、先導枠で応募し非採択だった場合、自動的に普及枠に応募があったものとみなします。
①普及枠:炭素貯蔵効果が期待できる中大規模木造建築物の普及に資するプロジェクト
②先導枠:先導的な設計・施工技術が導入されるプロジェクト
ただし、次のプロジェクト等は募集の対象になりません。採択後にこれらに該当することが判明した場合は採択が取り消されます。
・設計のみでその後の整備を伴わないプロジェクト
・事業の採択・補助金交付決定以前に既に着手している実施設計※1及び建設工事※2
※1:実施設計の着手とは、実施設計の作業を開始した時点をいう。
※2:建設工事の着手とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事又は根切り工事に係る工事が開始された時点をいう。
・具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や資金計画が伴わない事業の提案、事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案
・公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業※を目的とするもの
※風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等
(2)募集する事業の要件
① 普及枠
次のⅰからⅸまでの全ての要件に適合すること
- ⅰ 主要構造部※に木材・木質材料を使用する次のアからウまでのいずれか。
※ここでいう主要構造部とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)第2条第五号に掲げる主要構造部及び同法施行令第1条第三号に掲げる構造耐力上主要な部分(基礎・基礎ぐいを除く。)をいう。 - ア 木造の建築物(主要構造部の全てを木造とした建築物をいう。
- イ 建築物の部分が木造の建築物(立面混構造や平面混構造などのように、木造部分と木造以外の部分の床面積を明確に切り分けられる構造の建築物をいう。この場合、補助金の算定のため、木造部分と木造以外の構造の部分の設計費、建設工事費が明確に切り分けられること。
- ウ 補助対象部分※の主要構造部に床面積1㎡あたり0.05㎡以上の木材・木質材料を使用する混構造の建築物
※主要構造部に木材・木質材料を使用している部分。この場合、補助金の算定のため、主要構造部に木材・木質材料を使用している部分と、それ以外の部分の設計費、建設工事費が明確に切り分けられること。 - ⅱ 整備する建築物が、次の表に掲げるもの(建築基準法上、耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるものに限る)であること。
共同住宅等・事務所 : 階数が4以上のもの
非住宅(事務所を除く。) : 延べ面積が3,000㎡を超えるもの 又は 階数が3以上のもの - ⅲ 整備する建築物が、不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するものとして、次のアからオまでに掲げる用途のいずれかのもの。
- ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- イ 病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
- ウ 学校、体育館、博物館、美術館、図書館 等
- エ 百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗 等
- オ 事務所 等
- ※整備する建築物の用途は、建築基準法における扱いに準じる。
- ※上記の用途とそれ以外の用途の組み合せた複合的な建築物の場合、上記の用途以外の用途の部分は本事業の対象から除く。この場合、本事業の要件は、本事業の対象となる用途の部分に対して適用する。
- ⅳ 多数の利用者等に対する木造建築物の普及啓発に係る取組として、次のアからエまでの全てを満足するものであること。
- ア 本事業により整備された建築物及びその情報について、竣工後に内覧会や地域のイベントに使用する等、多数の者の目に触れることを計画するものであること
- イ 国土交通省又は評価事務局の求めに応じ、補助事業者の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害する恐れのない限り、木造建築物の普及に資する設計、施工等に関する技術情報(設計図書等)を公表すること。また、床を木造とするものにあっては、竣工時に評価事務局が指定する方法により床衝撃音データを取得しその結果を当該床の断面図とともに国土交通省へ提供すること(国土交通省では、提供された図面及びデータについて、木造建築を検討する各事業者に向けた参考情報とするため、個別の物件が特定されないようにした上で公表する予定。)。
- ウ 国土交通省が建設工事費、修繕費、維持管理費等に関する情報を整理し建築物の諸元と併せて公表することに協力すること
- エ 次のいずれかの方法により、炭素貯蔵量を算定・表示すること
- ・「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」(令和3 年10月1日付3林政産第85号)に基づく方法
- ・上記と同等の方法で、他の評価機関や評価方法により算出・表示する方法
- ⅴ 新築の建築物は、原則として、住宅部分においてはZEH水準※1、非住宅部分においてはZEB 水準※2に適合すること。ただし、令和6年度においては【P】、CASBEEのSランク又はこれと同等以上の性能を有するものとして第三者評価を取得するものにあってはこの限りではない。
- ※1:強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)をいう。以下同じ。)を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。
- ※2:再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から用途に応じて30%削減又は40%削減(小規模(300㎡未満)は20%削減)となる省エネ性能の水準をいう。
- ⅵ 整備するものが住宅である場合、当該住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域※1又は土砂災害に係る災害危険区域外※2に存すること。
- ※1:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。
- ※2:建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)
- ⅶ 整備するものが住宅等※である場合、当該住宅等は、居住誘導区域外に存し、原則として都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅等に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものでないこと。
- ※都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項の規定に基づく住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるものをいう。
- ⅷ 伐採後の再造林や木材の再利用等に資する取組として、次のアからエまでのいずれかの取組がなされること。
- ア 持続可能な森林から産出された木材※を使用すること
- ※合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)又は木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日林野庁)に基づき合法性が確認された木材をいう。
- イ 再利用木材を使用すること
- ウ 解体後の再利用を念頭においた木質部材を使用すること
- エ その他これらと同等以上の取組がなされること
- ⅸ 原則として、令和6年度中に実施設計又は建設工事に着手し、令和6年度予算として補助対象の出来高に応じた補助対象の支払いが完了すること。
② 先導枠
①普及枠の要件並びに次のⅰ及びⅱに適合すること
- ⅰ 構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術が導入されるとともに、耐久性にも十分な配慮がなされた事業計画であること。
- (評価委員会における評価の視点)
- ・構造・防火面において、次のアからウに掲げる木造化に係る設計・施工技術に相当の工夫が認められ、かつ当該設計・施工技術が他の事業者の参考になるなど普及性や応用可能性が期待されるものを高く評価する。
- ア 新たな技術の導入
- イ 既往技術の新たな組合せの導入
- ウ 過去に実施された木造プロジェクトにおける課題を踏まえ改善・改良した技術の導入により木造化を実現 等
- ・近年の建築基準法改正等により可能となった設計方法等を活用した取組※1を高く評価する。
- ・木造建築物の耐久性確保に関し普及性や応用可能性が期待される取組※2を高く評価する。
- ※1:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)による防火規定を踏まえた取組 等
- ※2:耐久性に関する第三者評価の取得、雨水や紫外線などの劣化外力に対する設計上の配慮、結露を防止するための設計上の配慮、水分の滞留を抑制するための設計上の配慮、使用環境を考慮した適切な材料の選択、維持管理・メンテナンス等に関する十分な配慮 等
- ⅱ 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなど木材利用に関する建築生産システムについて先導性を有する計画であること。
- (評価委員会における評価にあたっての視点)
- ⅰに掲げる新たな技術等の導入による木造化やその他の部分の木造化の取組について、普及に向けたコスト面での配慮がなされているもの※を高く評価する。
- ※例えば次のような取組が挙げられる。
- ・工場における効率的な生産や、部材製造・設計・施工プロセスの一体的デジタル化等により、現場での施工を容易にするための工夫がなされ、生産性の向上や工期の短縮が図られているもの
- ・一般流通材の活用や、寸法の規格化等の標準化に取り組む木質材料の使用により、木材調達
- ・加工コストや木材調達期間の合理化が図られているもの
- ・地域の工務店や建設事業者等で対応可能な設計・施工技術を採用することにより、特別な技術・ノウハウ等に係るコストが抑えられたもの
- ⅲ 建築物の木造化に係る先導的な技術について、竣工後にその内容を検証し、とりまとめて公表すること。
- (検証内容の例)
- ・新たな技術の導入等によって得られた効果や普及に向けた課題の検証
- ・整備コストの低減に関する検証
2. 公募期間
| 公募期間 | 提出期限 | 採択時期の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1回 | 令和6年4月1日(月) ~令和6年4月30日(火) | 令和6年4月30日(火)17時必着 | 令和6年7月上旬頃 |
※2回目以降の募集は、1回目募集の応募状況を踏まえ実施するかどうかを検討します。
3. 対象事業者
本募集への応募者及び補助を受ける者は、原則として本募集に応募したプロジェクトを実施する予定の建築主とします。ただし、建築主を代表者とし共同で応募することや、応募や諸手続において建築主と代理契約を交わした者が実務を遂行することも可能です。
なお、次の①又は②に該当する者※は、原則として本事業への応募は認められません。
① 過去3カ年以内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)であること
②暴力団または暴力団員であること、ないしは、暴力団または暴力団員と不適切な関係にあること
※応募にあたっては、上記①及び②への該当の有無を申告していただきます(様式2の「6 応募者に関する確認事項」欄を参照)。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。
4. 応募方法等の詳細
本ホームページに掲載する募集要領(令和6年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。
5. よくある質問
よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)
「優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局」
〒104-0043 東京都中央区湊3丁目4-4 中央山田ビル2階
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
電話:03-6262-8220(月~金 11:00~16:00(祝日・年末年始を除く))
お問い合わせメールアドレス:sendo-shien@kiwoikasu.or.jp
※当面の間、メール対応とさせていただきます。